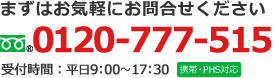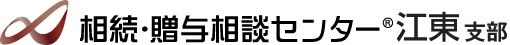古い遺言書は定期的に見直そう。 遺言書作成や保管の際の注意点
遺言書は、相続が開始したときに遺産分割を円滑に進めるうえで役に立ちますが、注意すべき点もあります。今回は、作成した遺言書の内容が法的に有効なのか、また、いつまで有効なのかなど、遺言書の作成や保管にあたって注意すべき点について紹介します。
遺言書の内容にも注意が必要。法定遺言事項とは?
遺言は財産の分け方などについての生前の意思表示です。その内容を記した遺言書の作成については、『公正証書遺言』や『自筆証書遺言』など、法律によって厳格に定められています。この法律に従って正しく作成していなければ、遺言が無効になることもあります。
ほかに、遺言書の記載内容についても法的な効力をもつ事項が定められており、これを『法定遺言事項』といいます。法定遺言事項以外の事項を記載しても、その内容には法的な効果は生じません。この法定遺言事項は、相続に関する事項、その他の財産に関する事項、身分に関する事項、遺言の執行に関する事項に分類されます。
主な内容は次の通りです。まず、相続に関する事項には、相続分の指定または第三者への指定の委託、遺産分割方法の指定または第三者への指定の委託および遺産分割の禁止、推定相続人の廃除または廃除の取り消し、遺留分侵害額の負担割合の指定などがあり、そのほかの財産に関する事項には、遺贈、信託の設定などがあります。また、身分に関する事項には、非嫡出子の認知、未成年後見人や後見監督人の指定があり、遺言の執行に関する事項には、遺言執行者の指定または第三者への指定の委託などがあります。
なお、法的遺言事項以外の内容は、法的な効果は生じませんが、『付言事項』として記載することができます。なぜ遺産をこのように分けたのかなどを記載して、相続トラブルを防いだり、遺言書を通じて家族への感謝の気持ちや葬儀や納骨についての希望を伝えたりする場合などにも用いられることがあります。
遺言書に有効期限はある?古くなった遺言書の注意点
先に紹介したように、遺言書が有効かどうかは、その遺言書の方式や記載内容によって決まります。
いったん有効に成立した遺言書は、作成した日から長い年月が経っていても、それを理由として無効とされることはありません。つまり、遺言書に有効期限はありません。
ただし、公証役場で保管されている公正証書遺言や法務局で保管されている自筆証書遺言書の原本には、それぞれ遺言者の死亡後50年間などの保管期間が設定されていますので、忘れないようにしておくとよいでしょう。
遺言書には有効期限がないため、一度作成した遺言書は亡くなるまでそのままにしておくケースがあります。しかし、遺言書を作成後、長期間放置していると、遺言書の作成当時と状況が変わっていることがあります。たとえば、記載していた相続人が先に亡くなってしまった、引き継ぐ予定だった財産の内容が変わってしまった、または長い年月の間に保有していた財産の価値に大きな変化が生じていたといったケースが考えられます。
遺言書の内容がこうした相続人や相続財産の変化を反映していないと相続トラブルにつながる場合がありますので、トラブルを避けるためにも遺言書は定期的に見直し、必要に応じて書き換えるなどの対応をするのがよいでしょう。
遺言書の作成について悩むようであれば、専門家に相談することをおすすめします。
電話でのお問い合わせは0120-777-515